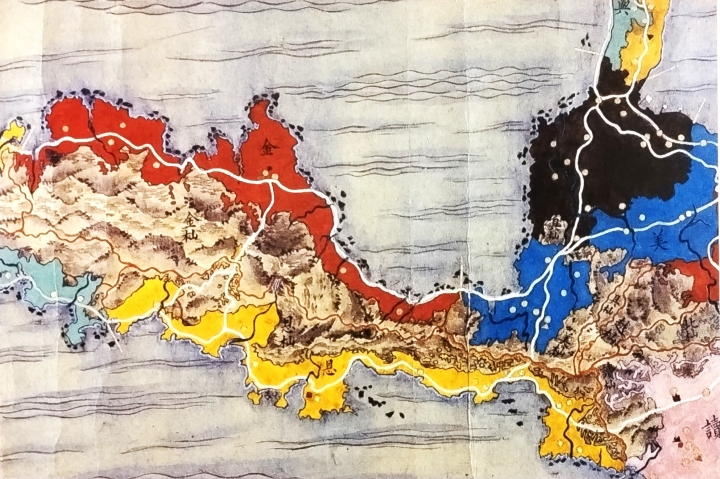沖縄の落ち着きが今もしっかりと残る確かな空間
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

沖縄と仲泊、そして今という時代について
沖縄は暑い。
窓の外にはブーゲンビリアがほぼ一年中咲いている。
台風から人々の暮らしを守るフクギの緑は濃い。
が、そこは亜熱帯であり常夏の熱帯ではない。
11月中旬には、新北風と呼ばれる季節風が吹き、その後ひと月ほどで短い冬が訪れる。
とは言え、その1月に緋寒桜が咲く。鶯が鳴き始めるのも同じ頃。
山原と呼ばれる沖縄本島北部には、植物が鬱蒼と茂る森が拡がる。
そこにはイタジイを代表とするブナ科の樹々に混じってヘゴと呼ばれるシダ植物が群生。
常緑の緑に遮られる陽光は真上からしか届かない。
その森が沖縄の命を育む。
今、沖縄の水道には太陽から恵みを受けた山原の水が流れている。
恩納村仲泊。琉球王朝時代に首里王府と山原を結ぶ「宿道(しゅくみち)」と呼ばれる古道の中程に位置した由緒ある集落。
「コテージ仲泊」は、落ち着いた暮らしを大切にする心豊かな人々が住む集落の一角をお借りして、その土地に生まれ育った棟梁が弟さんと二人で建てた手造りの宿。そこには特別なものは何もない。あるのは「仲泊」という空間。
時間を捉え直す。風を聴く。
一人一人が取り戻す何かがきっとある。
集落の片隅にたたずむ手作りのコテージで過ごす時間
それは、大人が自分を大切に見直す時間。木陰で太陽の巡りに体を預ける。日常の延長であるホテルでは味わえない静かな時間。
子供は走る。子供は唄う。笑い、泣き、眠る。思い切り走らせたい。都会暮らしから、子供を自然に還す時間。
コテージ仲泊はそんなひと時を提供する旅の宿です。
動画、写真をインスタで配信しています
・・・沖縄の毎日のさりげない出来事や風景を、コテージ仲泊からのお便りとして皆様にお届けしています・・・・・・・・